「今日もご飯作るの、正直ちょっとしんどいな…」
「今日もまた献立を考えるのか…」
「帰ってきてからご飯の支度、ちょっと気が重いな」
そう感じてしまう日って、誰にでもありますよね。

私も共働きで接客業のパートをしているので、こういう日は本当によくわかります。
勤務が終わっても、今度はご飯作りが待っていると思うと、心も体もぐったりしてしまいますよね。
だからこそ、共働き家庭では“常備食品”をうまく活用することで、
- 日々のご飯作りの負担をグッと減らすことができる
- 買い物や調理の手間を減らせる
- 「作りたくない日」でも安心できる
といったように、毎日のご飯づくりをぐっとラクにすることができます。
そんなふうに、常備食品は小さなストレスを減らしながら、気持ちにも時間にも余裕をつくってくれる存在です。



私も常備食品に助けられた日が何度もあり、今では“お守り”のような存在になっています。
この記事では、そんな私自身の経験も交えながら、忙しい日でも無理なく使える常備食品の活用法をご紹介していきます。
- 共働きで毎日のご飯作りが負担に感じている方
- 「あと一品がない…」と夕飯づくりに悩む日がある方
- ご飯を作りたくない日でも、できるだけ整った食事にしたい方
- 買い物や調理の手間を減らしながら、時短でごはんを用意したい方
- 外食やお惣菜に頼りすぎず、家で無理なく食事を続けたい方
- 常備食品を使った簡単レシピやストックのコツを知りたい方
「今日はご飯を作りたくない…」という日があっても大丈夫です。
常備食品を少し整えておくだけで、無理をしない“続けられる食卓”を作ることができます。



私自身、共働きで料理に疲れてしまった経験があるからこそ、同じように悩む方に役立つ情報をまとめました。
それではまずは、なぜ常備食品が共働き家庭の負担を減らしてくれるのか、その理由からお話しします。
共働き夫婦にとって「常備食品」が心強い理由


毎日のように、
「夕飯、何作ろう…」
「冷蔵庫に卵と小松菜が残ってたし、これで何作れるかな…?」
と、献立に悩むことはありませんか?
仕事を終えて帰宅するころには体力も気力も残っていないことが多く、
「疲れたし、もう外食でいいかな…」
「お惣菜に頼っちゃおうかな。」
と思う日もありますよね。



私も、以前は冷蔵庫や野菜室の在庫を思い出しながら献立を考える日が続いていました。
家にあるもので何とかできるか、何か買い足すべきかを考えているだけでも、頭の中がいっぱいになってしまうんですよね。
ですが、そんな日々の悩みを少しでも軽くしてくれるのが、常備食品です。
常備食品があることで、
- 忙しい日でもご飯作りのハードルが下がる
- 買い物の回数を減らして時間と体力を節約できる
- 「今日は作れないかも」という不安が減る
と、心にも時間にも余裕が生まれます。
この章では、共働き家庭の毎日に常備食品がどんな形で役立つのかを、わかりやすく3つのポイントでご紹介します。



私も、常備食品に何度も助けられてきたからこそ、“自分を責めずに過ごせる夕方”を少しずつ増やせた気がします。
では、具体的にどんなシーンでその心強さを感じられるのか、1つ一つお話ししていきますね。
1.忙しい平日の“あと一品”がすぐできる
共働き夫婦にとって「常備食品」が心強い理由の1つ目は、忙しい平日の“あと一品”をすぐに作れることです。
忙しい平日の夕食づくりでよくあるのが、「あと一品ほしいけれど、もう作る気力が残っていない…」という状況です。
メインのおかずを作ったあとのキッチンで、
「副菜まで作る体力はもうない…」
「でも栄養のバランスは少し気になる…」
と感じる日、ありませんか?



私も同じで、仕事帰りの夕方は「もう立ち続けるのもしんどい…」と思うことがあります。
そんなときに役立つのが、常備食品です。
常備食品があれば、火を使わずに数分で“あと一品”を追加できます。



たとえばわが家では、次のようなものがよく活躍しています。
- 卵
卵焼きやスクランブルエッグなら3分ほどで完成
冷蔵庫の常連食材でアレンジも自在 - 冷凍野菜
ほうれん草やブロッコリーをレンジで1〜2分加熱してマヨネーズを添えるだけ
彩りも栄養もプラス - レトルト食品
カレー・煮物の素・スープなどを温めるだけで立派な一品に - 冷凍揚げ物や惣菜
トースターやレンジで温めるだけで即完成
お弁当おかずにも◎ - 冷凍弁当
ご飯もおかずもセットでレンジで温めるだけ
手を動かす余裕がない日でも、しっかり食事が取れる心強い味方 - 缶詰
ツナやサバ缶、焼き鳥缶など、開けるだけで食べられるお助け食材
温めずにそのまま出せるので、疲れきった日の“あと一品”にもピッタリ
どれも準備が簡単で、疲れ切ったときでも“無理なく食卓を整える”ことができます。
ですが、常備食品をただ置いておくだけでは十分に活かせません。



続けやすくするためには、次の3点が大事です。
- すぐ使える状態で置いておくこと
- 飽きないように種類をいくつか用意しておくこと
- 自分たちの生活リズムに合うものを選ぶこと
共働き家庭は、仕事と家事の両立で体力も時間も限られています。
だからこそ、常備食品は“頑張らなくてもごはんが整う仕組み”としてとても役立ちます。



そんな小さな工夫の積み重ねが、忙しい日々の支えになっていくはずです。
2.お惣菜に頼らなくても、“ちょっと整う”ごはんが作れる
共働き夫婦にとって「常備食品」が心強い理由の2つ目は、外食やお惣菜に頼らなくても、手軽に“ちょっと整う”ごはんが作れることです。
仕事が忙しい日や疲れた日は、
「今日はもうお惣菜でいいか…」
「帰りに何かテイクアウトでも買って帰ろうかな…」
と思うこと、きっと誰にでもありますよね。



私も同じで、疲れ切った日にお惣菜に頼ってしまうことは何度もありました。
でも、そんな日が続いたときにふと、
「ちょっと野菜が足りてなかったかも…?」
「ここ最近、栄養が偏っていたかもな…。」
と気になるようになったんです。



ある日、夫から「最近、野菜食べてないね?」と言われてハッとしました。
そこで食生活を見直しを始めたときに役立ってくれたのが、常備食品でした。
実は、常備食品を上手に組み合わせるだけで、調理の手間をかけずに栄養をプラスできるんです。



たとえば、わが家では次のような組み合わせをよく使っています。
- レトルトカレー+ゆで卵
半熟でも固ゆででもOK
たんぱく質が増えて満足感もアップ - インスタント味噌汁+乾燥わかめ+刻みねぎ
ミネラルと食物繊維をサッと追加できる - 冷凍ご飯+レトルト丼の素(牛丼・親子丼など)+刻みねぎ
温めてのせるだけ
彩りもよく、野菜も少し加えられる - 冷凍うどん+温泉卵+めんつゆ
疲れた日にぴったり
火を使わずに一品完成
どれも少し足すだけで“ちゃんとしたごはん”になる簡単な方法です。



常備食品を少しずつ揃えるようになってから、夜ごはんづくりがぐっとラクになりました。
「手元にあるものでなんとかなる」と思えるだけで、不思議と気持ちも軽くなるんですよね。
常備食品の魅力は、
- ラクをしても、きちんと感が出せること
- 無理せず続けられる食のリズムを作れること
この2つにあります。



忙しい毎日だからこそ、「できることを、できる範囲で」が大切ですね。
無理をしない工夫が、ごはん作りを続けるいちばんのコツだと感じています。
3.常備食品があれば、無駄買いや外食の出費を防げる
共働き夫婦にとって「常備食品」が心強い理由の3つ目は、無駄な買い物や外食の出費を防げることです。
仕事終わりに、
「今日はもうご飯作りたくないな…」
「冷蔵庫、何が残ってたっけ…?」
「スーパー寄る気力もないな…」
と思いながら、ついコンビニやスーパーに立ち寄ってしまうこと、ありませんか?
疲れていると判断力が鈍り、
- 献立が決まらず、何を買えばいいか決められない
- 店内をぐるぐる回って、気づけば30〜40分経過
- お惣菜だけのつもりが、デザートまで手が伸びる
- 割引シールにつられて、予定外のものをカゴへ
- 帰ってから「あれ、必要なものが揃ってない…」と落ち込む
こんな“買い物疲れ”の経験、きっとあるはずです。



私も経験したことがあります…。
そんな負担を減らしてくれるのが、家に置いておける常備食品です。
常備食品があるだけで、
- 「足りないから買わなきゃ」という焦りがなくなる
- 外食やテイクアウトの頻度が減る
- 結果的にムダな出費や衝動買いが減る
という嬉しい効果があります。



私自身、以前は「とりあえずスーパーへ行く」が当たり前になっていました。
しかし、常備食品を少しずつ整えてからは、買い物に行かない日が増え、「今日は家にあるもので大丈夫」「無理して買い物に行かなくてもいい」と思えるようになりました。
こうした“ちょっとした余裕”の積み重ねが、
- 暮らしを穏やかに整えてくれる
- ご飯づくりにも優しい流れをつくってくれる
そんな良い流れを生んでくれます。
常備食品は頑張るためのものではなく、無理をしないための仕組みです。



自分のペースで、できるところから取り入れていきたいですね。
この章では、共働き夫婦にとって「常備食品」が心強い理由について詳しくお話ししてきました。
- 忙しい平日の“あと一品”がすぐできる
- お惣菜に頼らなくても、“ちょっと整う”ごはんが作れる
- 常備食品があれば、無駄買いや外食の出費を防げる
共働き生活では、仕事の疲れや時間のなさから「今日のご飯どうしよう…」と悩む日もありますよね。
そんなとき、常備食品は“安心の味方”になってくれる存在です。
常備食品があるだけで、
- 「足りないから買わなきゃ」という焦りがやわらぐ
- あと一品を作る余裕が持てる
- お惣菜や外食に頼る回数が減る
- 買い物の回数が減り、ムダな出費や衝動買いを防げる
といった、小さくもうれしい変化が積み重なっていきます。



私も、ご飯を作りたくないときに「常備食品があってよかった」と思えた瞬間が何度もありました。
だからこそ、常備しておく価値は十分にあると感じています。
常備食品は、頑張るためのものではありません。
“無理をしなくてもなんとかなる”を支えてくれる、暮らしの土台のような存在です。
ぜひ、あなたの生活リズムに合った形で、少しずつ取り入れてみてください。



きっと、明日のご飯づくりが今より少しラクになるはずです。
我が家で役立った常備食品リスト【常温ストック編】
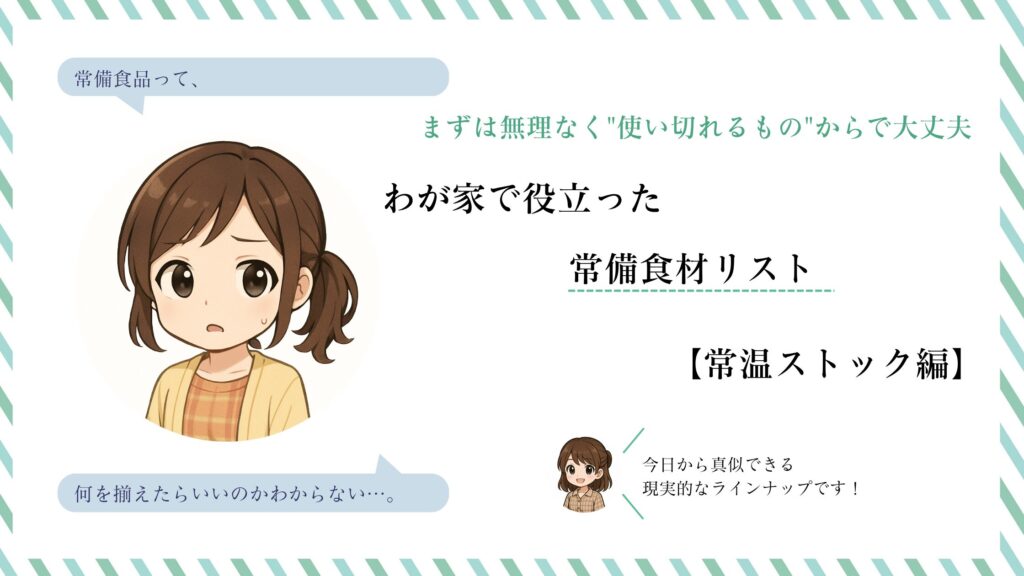
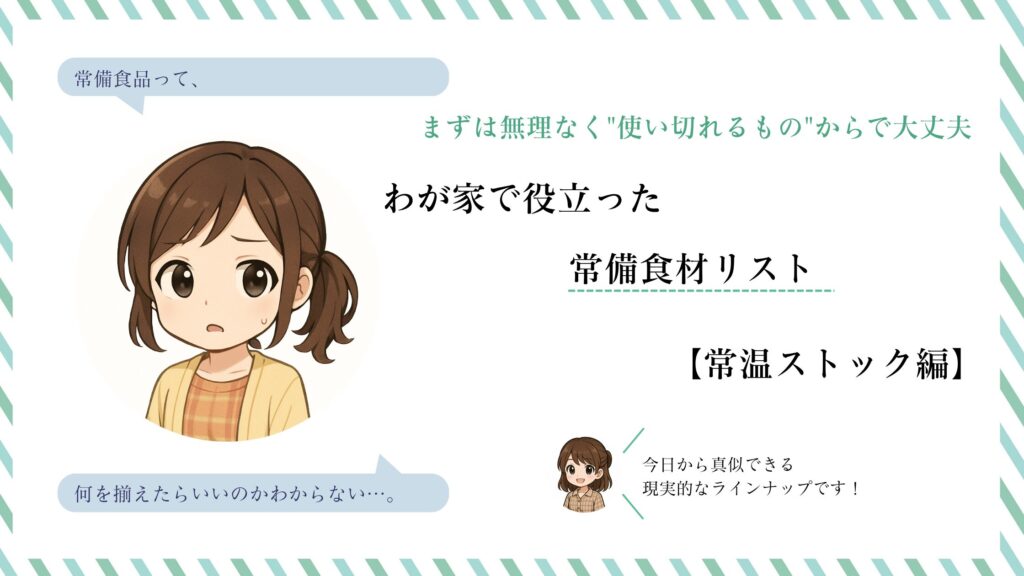
共働き家庭にとって「常備食品があると助かる」ということはわかっていても、
- 何を揃えたらいいのかわからない
- うちの暮らしに合う“ちょうどいい量”ってどれくらい?
- 買っておくと安心なものと、意外となくても困らないものの違いは?
- 置きすぎて賞味期限を切らせたくないし、少なすぎて困るのも避けたい…
と感じる方も多いのではないでしょうか。



私自身も共働きで暮らしながら、「常備食品って本当に役立つの?」と迷っていた時期がありました。
でも、少しずつ試していくうちに「これは置いておくと本当に助かる」という定番が見えてきたんです。
この章では、私が実際に使ってみて“忙しい毎日に本当に役立った”と感じた常温ストックの常備食品リストを、用途別にわかりやすく紹介します。
どれもスーパーやネットで手軽に買えるものばかりです。特別なものはありませんが、「今日は何も作れない…」という日でも支えになってくれる、小さな安心ストックです。
このあと、冷蔵庫や冷凍庫に常備しておくと便利な食材も紹介しています。



先にそちらをチェックしたい方は、こちらからどうぞ。



まずは、日々の食事の土台になる「主食系ストック」から紹介していきます。
1.主食系ストック
我が家で役立った常備食品リスト【常温ストック編】の1つ目は、主食系ストックです。
仕事終わりはできるだけ早く食事を済ませたい日も多いですよね。
ですが、
「おかずはあるけど、炊飯のスイッチを押す気力がない…」
「今すぐ食べたいのに、ご飯がまだ炊けていない…」
そんな状況、きっとどの家庭でも一度は経験があるのではないでしょうか。



わが家でも同じでした。
特に夫は、帰宅するとすぐにご飯を食べたいタイプで、ご飯が炊けていないだけで食事が遅れてしまい、気まずい空気になることもあったんです。
そこで頼りになるのが、常温で保存できる主食ストックです。
主食ストックは「炊かずに食べられるご飯」や「茹でるだけの麺類」を少し置いておくだけで、
- ご飯を炊く余裕がないとき
- とにかく早く食事を用意したいとき
こんなときの“時間の味方”になります。



常備しておくと、意外と助かるメリットが多いんです。
- 買い物や炊飯の手間を減らせる
- 疲れた日でもすぐに食事が整う
- いざというときに安心感がある



わが家でも、“あると便利”な主食ストックをいくつか置いています。
実際に役立っているものを紹介しますね。
- パックごはん
電子レンジで約2分で食べられる
すぐ食べられる安心ストック - 冷凍ごはんや冷凍焼おにぎり
まとめ炊きしておくと便利
夜食にも◎ - レトルトのおかゆや雑炊の素
体調がすぐれない日や食欲がない日にピッタリ - 食パンやロールパン
スープを足すだけで一食完成
朝にも夜にもピッタリ - 乾麺(うどん・そば・パスタなど)
茹でるだけで主食になる
残りおかずと合わせやすい
主食系ストックを準備しておくだけで、
- 「ご飯をどうしよう…」という焦りが減る
- 気持ちに余裕ができる
- バタバタしないで済む
そんな“小さな安心”につながります。
まずは無理なく、週末に1〜2種類を買い足すところからはじめてみるのがおすすめです。



主食のストックがあるだけで、「今日はなんとかなる」と思える日がきっと増えていきますよ。
2.レトルト食品
我が家で役立った常備食品リスト【常温ストック編】の2つ目は、レトルト食品です。
仕事で疲れて帰ってきた夜、
「もう何も作りたくない…」
「でも今日の夕飯どうしよう…」
そんなふうに感じる日、ありませんか?



私も同じで、帰宅後は「できるだけ時短で簡単に済ませたい」と思う日がよくあります。
そんなときに頼りになるのが、温めるだけで食べられるレトルト食品です。
レトルト食品は、基本的に電子レンジで温めるだけなので、
- 体力が残っていない日
- キッチンに立つ時間をできるだけ短くしたい日
そんな場面で無理なく食事を整えられる、心強い味方です。



レトルト食品を常備しておくと、こんなメリットがあります。
- 温めるだけで、すぐにしっかり食事が整う
- 体力・気力がない日でも“ちゃんとごはん”がとれる
- 忙しい日や体調不良のときにも安心



私もレトルトを常備するようになってから、「今日はもう無理…」と感じる日の不安が減りました。
ここからは、実際に我が家でよく使っているレトルト食品を紹介します。
- レトルトカレー
温めるだけで一品完成
種類が豊富で飽きにくい - パスタソース
茹でたパスタに絡めるだけ
ストックしておくと安心 - 丼の素(親子丼・中華丼など)
ご飯にのせるだけで満足感のある食事に
時短なのに満足感がしっかりあるのがうれしい
レトルト食品は、
- 常温で長く保存できる
- 調理道具をほとんど使わずに食べられる
- 無理をしなくても栄養を確保できる
という点で、忙しい共働き家庭にはとても便利なアイテムです。



「手抜きに見えないかな…?」と気になることもあるかもしれませんが、私は今では“自分を助けるための選択肢のひとつ”だと考えています。
レトルトがあるだけで、“今日は無理せず過ごせる”と思えるようになります。
買い物をしたときに、レトルトコーナーを覗いてみてください。



買い物をするときにレトルトコーナーを覗いてみるだけで、「これ、置いておくと安心かも」というアイテムが見つかるはずですよ。
3.スープ・汁物ストック
我が家で役立った常備食品リスト【常温ストック編】の3つ目は、スープ・汁物ストックです。
仕事や家事で疲れているとき、
「おかずは用意できたけど、汁物まで作る気力がない…」
「もう一品ほしいけど、鍋を出すのは面倒…」
そんな日もありますよね。



私も同じで、疲れがたまっているときほど「あたたかいものを少しだけでも飲みたい」と思うことがあります。
でも、一から味噌汁やスープを作るのは意外と手間がかかって大変ですよね。
そんなときの“ひと息”を支えてくれるのが、スープや汁物のストックです。
スープ系の常備食品は基本的にお湯を注ぐだけなので、
- 主菜はあるけれど“少し温かさを足したい”とき
- 朝食を手早く済ませたいとき
- 食欲が落ちていて、軽く済ませたいとき
- 洗い物を増やしたくない日
こんな場面で“食卓を整えてくれる”心強い存在です。



スープや汁物を少し置いておくだけで、こんなメリットがあります。
- 食事全体の満足感が増す
- 栄養バランスを整えやすくなる
- 少量でも満足感を得やすい
- 食べやすく、体調に合わせやすい



わが家でもスープ類は切らさないようにしています。
とくによく使うのは次のようなものです。
- インスタント味噌汁
具付きタイプは満足感があり、わかめ・豆腐・なめこなど種類も豊富 - お吸い物の素
焼き魚やおにぎりと合わせて和食にピッタリ - わかめスープ
お弁当や夜食にも便利でまとめ買いしやすい
スープ・汁物のストックは、
- 1人分から準備できる
- 家族の帰宅時間がバラバラでも出しやすい
- 洗い物が少なく後片付けがラク
- 必要なときにすぐ作れる
という点でも共働き家庭に向いています。



私自身、ご飯とおかずだけだと「もう少し何かほしいな…」と感じることがありますが、スープを添えるだけで食事が落ち着きます。
まずは、家族が好きな味を2〜3種類だけ決めてストックしておくのがおすすめです。
無理をしなくても整う“ちいさな仕組み”があるだけで、「今日はスープがあるから大丈夫」と思える日が増えていきます。



「今日はスープがあるから大丈夫」と思える日がきっと増えていくはずです。
この章では、「我が家で役立った常備食品リスト【常温ストック編】」について詳しくお話ししてきました。
- 主食系ストック
- レトルト食品
- スープ・汁物ストック
忙しい平日は、「今日はもうご飯を作る気力がない…」という日もありますよね。
そんなときでも、常温の常備食品が少しあるだけで“なんとかできる仕組み”になります。



私自身、主食・おかず・スープを少しずつ常備するようになってから、「今日はご飯どうしよう…」という不安が減りました。
完璧に頑張れない日があっても、“食べることを諦めなくていい”という気持ちになれたんです。
常備食品は、ラクをするためだけのものではありません。
毎日続くごはんづくりを“無理なく続けられる形”に整えてくれる心強い味方です。
ぜひ、あなたの家でも、無理なく続けられる常備食品から少しずつ取り入れてみてください。



きっと「これがあるだけで安心」と思える日が増えていくはずです。
我が家で役立った常備食品リスト【冷蔵・冷凍ストック編】
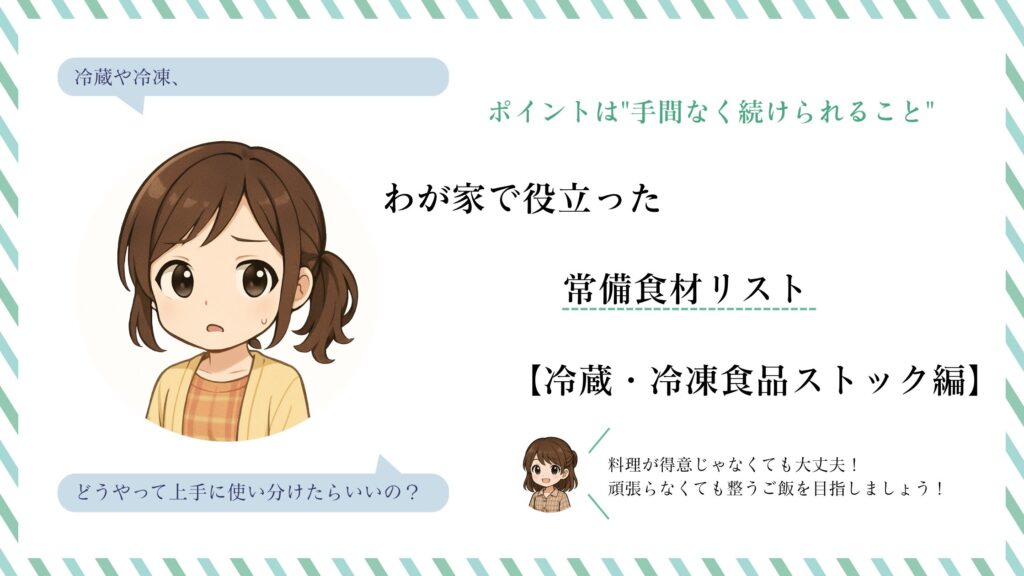
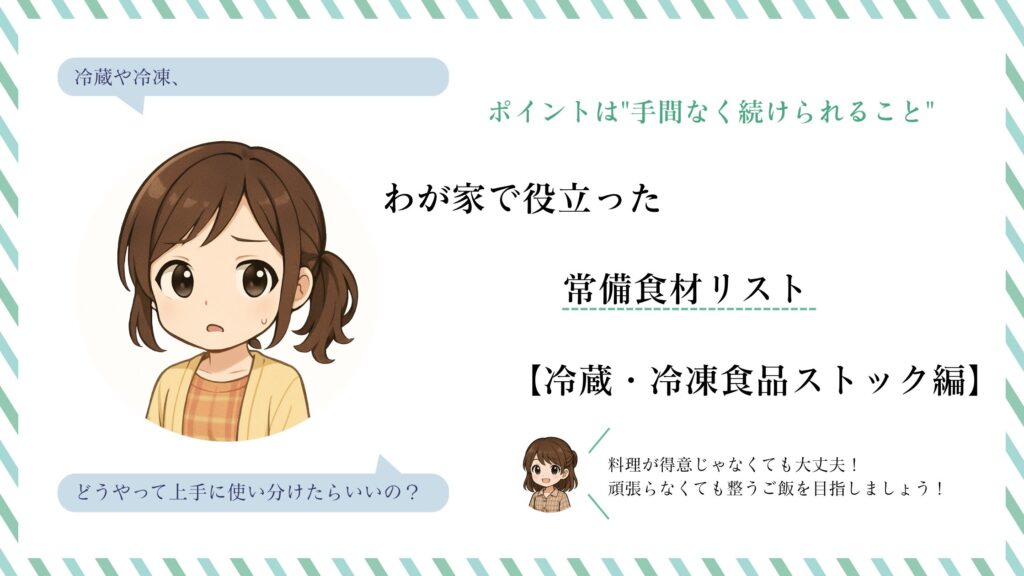
仕事や家事を終えて帰宅したあと、
「冷蔵庫に何もない…」
「仕事の疲れで、今日はもう作る気力が残っていない…」
そんなふうに感じたことはありませんか?



私も同じで、仕事終わりの疲れと空腹が重なると、献立を考える気力すらなくなってしまうことがあります。
でも、冷蔵庫や冷凍庫の中身をうまく整えておくと、「今日はもう作れないかも…」という日でも、“なんとかなる”と思えるようになります。
とはいえ、冷蔵庫や冷凍庫に食材をため込みすぎると、
- 使い切れずに余らせてしまう
- 冷蔵庫に入りきらなくなる
- 何が残っているか把握できず、同じものをまた買ってしまう
- 気づけば賞味期限が切れていた
という“もったいない悪循環”にもつながりがちです。



だからこそ、冷蔵庫・冷凍庫には「無理なく使い切れる常備食品」を選ぶことが大切なんです。
この章では、実際に我が家で役立った【冷蔵・冷凍ストック編】の常備食品を紹介していきます。
どれも身近な食材ばかりですが、少しの工夫で“ご飯づくりのプレッシャー”を軽くしてくれる心強い味方です。
無理せず続けられる冷蔵・冷凍ストック術で、「今日は何も作れない…」という日にもそっと助けてくれます。



それでは、まずは冷蔵ストックから紹介します。
1.冷蔵ストック編|共働きに便利な常備食材リスト
我が家で役立った常備食品リスト【冷蔵・冷凍ストック編】の1つ目は、冷蔵庫の定番ストックを整えておくことです。
仕事や家事を終えて帰宅したあと、
「あと一品、何にしよう…」
と考え込んでしまうこと、ありませんか?



私も同じで、まずは冷蔵庫の中にあるもので何とかできないかと考え、レシピアプリを開いて時間だけが過ぎてしまうことがよくあります。
そんなときに支えてくれるのが、冷蔵庫の定番ストックです。
共働きの日々では、買い物に行く時間がとれなかったり、「今日はもう外に出たくない…」という日もありますよね。
そんなときでも、冷蔵庫に“すぐ使える食材”が少しあるだけで、ご飯づくりの負担がぐっと軽くなります。



わが家では、「日々のごはんにすぐ足せる」「短時間で一品になる」ことを基準に冷蔵ストックを選んでいます。
ここからは、実際に我が家で常備している食材をご紹介します。
- たまご
困ったときに使える万能食材
卵焼き・目玉焼き・炒め物にも活躍 - 豆腐
冷奴や味噌汁、丼ものの副菜に使える“やさしい一品”の材料 - 納豆
忙しい朝や疲れた夜に便利
ご飯にのせるだけで食事が整う - 刻みねぎ
汁物・冷奴・炒め物のトッピングに
料理の満足度がアップ - ベーコン・ハム
朝食にも夕食にも使いやすい
炒め物やスープの具材にも◎ - 牛乳・バター
朝食・スープ・簡単おかずに使える定番
常備しておくと安心 - マヨネーズ・ケチャップ
味つけに困ったときの“頼れる調味ベース”



私も、疲れて帰った夜は『もう何もしたくない…』と思うことがあるんです。
でも、今挙げたような冷蔵庫の定番だけで一品作れるので、“とりあえず何とかなる”と思えます。
ただ、便利さを重視するあまり使い切れずに奥で眠らせてしまう原因になってしまうかもしれません。
それでは、せっかくの“安心のためのストック”が、逆に負担になってしまいますよね。
だからこそ、ここからはムダにしないための選び方を押さえておくことが大切です。



わが家では冷蔵ストックを選ぶときに次の3つを意識しています。
- 賞味期限が短すぎないものを選ぶ
すぐに使い切れない食材はストックに不向き - 組み合わせやすい素材を意識する
単体で完結しない食材は出番が少ない - “あれば安心”という基準で揃えすぎない
種類より「使い切れる量」を優先
無理にたくさん詰め込む必要はありません。
自分の中で「これだけは置いておきたい」という冷蔵の定番を決めておくだけで十分です。



私も“定番の数点”を決めただけで、「一品足したいときも何とかできそう」という安心感が増え、小さな焦りが減ったと感じています。
冷蔵の定番を整えることは、毎日のごはんをスムーズにする小さな仕組みづくりです。
あなたの冷蔵庫にも、ぜひ“頼れるいつもの定番”を持ってみてください。



きっと「あと一品」の心強い味方になってくれるはずです。
2.冷凍ストック編|買い置きに便利なストック食材
我が家で役立った常備食品リスト【冷蔵・冷凍ストック編】の2つ目は、冷凍庫の定番ストックを上手に活用することです。
仕事や家事を終えたあとに、
「使おうとしていた野菜が傷んでしまっていた…」
「今日は買い物に行く余裕すらない…」
と、いうことはありませんか?



私も同じで、「明日使おう」と思って冷蔵庫に入れていた野菜をダメにしてしまったり、仕事終わりに買い物に行く気力が残っていない日があります。
これはもう、共働きあるあるですよね。
そんなときに頼りになるのが、日持ちしてすぐに使える冷凍ストックです。
冷凍食品が少しあるだけで、「今日は無理かも…」という日も食事づくりのハードルがぐっと下がります。



“とにかく使いやすいもの”だけを残した結果、わが家はこの形に落ち着きました。
- 冷凍野菜
ほうれん草・里いも・なす・オクラ・なめこ など
下ごしらえ不要で汁物・炒め物・副菜に - 冷凍パン
食パンやコストコのディナーロール など
忙しい朝や小腹満たしに - 冷凍肉・魚
お買い得なときにまとめ買いして小分け冷凍
そのまま冷凍すると劣化しやすいので、保存方法を工夫しています(※後述) - 冷凍弁当・冷凍パスタ
「今日はご飯づくりが無理…」という日の“お守りストック”
冷凍ストックの強い味方|グラッド プレスンシール活用法
冷凍ストックをより長く・おいしく保存するために欠かせないのが、グラッド プレスンシールです。
肉や魚をそのままパックごと冷凍すると、どうしても起きやすいのが「冷凍焼け」です。
表面が白っぽく乾燥してしまい、解凍後に固くパサついてしまいます。



そんな悩みを防いでくれるのが、密着性の高い保存シート グラッド プレスンシールです。
- グラッド プレスンシールとは?
-
アメリカ生まれのキッチン保存シートで、食材にぴったり密着して空気を遮断できるのが最大の特徴です。
通常のラップと違いシート同士がしっかり貼り合うため、液漏れやニオイ移りも防ぎやすく、冷凍保存との相性がとても良いアイテムです。



私は肉や魚を買ったら、すべてプレスンシールで包んでからジッパーバッグに入れて冷凍しています。
プレスンシールを使った冷凍保存をするメリットは4つです。
- プレスンシールを使った冷凍保存のメリット
-
- 空気を遮断しやすく、冷凍焼けを防ぎやすい
- 液漏れ・におい移りを防止
- 必要な分だけ切って使える
- ジッパーバッグと併用すれば長期保存もしやすい
グラッド プレスンシールを使うことで、まとめ買いした肉や魚も安心してストックできます。
「安い日に買いだめしたい」「食材を無駄にしたくない」という方には特におすすめです。



※さらに便利な使い方や保存手順は、別記事で詳しく紹介予定です。
とはいえ、冷凍食品は便利な反面、詰め込みすぎると
- 何がどこにあるのかわからない
- 似たような食材をまた買ってきてしまう
- 下のほうから“化石ストック”が発掘される
なんてことにもなりがちです。



そんな“冷凍庫の迷子”を出さないために、私が意識しているポイントは次の5つです。
- 冷凍庫に入りきる分だけ購入する
「安いから」と買いすぎない - 使い切れる量だけをストックする
1〜2週間で使い切れる量が目安 - 小分け・カット済みで保存する
調理にすぐ使える形にしておく - 置き場所のルールを決める
種類ごとに“定位置”を決める - 月1回の“使い切りデー”を作る
在庫をリセット&整理する習慣に
私自身、この5つを意識するようになってから、冷凍庫が使いやすくなり、
- 必要な食材をすぐ見つけられる
- 「結局使わずに捨てる」がなくなった
- 夜ご飯づくりのスタートが早くなった
という効果を感じています。
冷蔵ストックと同じく、冷凍ストックも増やすことより“回す”ことが大切なんです。
無理に完璧を目指さなくても大丈夫です。



あなたの冷凍庫にも、少しずつ“使いやすい仕組み”を作っていきましょう。
この章では、我が家で役立った常備食品リスト【冷蔵・冷凍ストック編】について、詳しくお話ししてきました。
- 冷蔵ストック編|共働きに便利な常備食材リスト
- 冷凍ストック編|買い置きに便利なストック食材
共働きの暮らしでは、毎日のご飯づくりにかけられる時間も体力も限られていますよね。
だからこそ、冷蔵庫や冷凍庫に“すぐ使える常備食品”があるだけで、「今日は何を作ろう…」「買い物に行けない…」という不安が減っていきます。



私自身も、冷蔵・冷凍ストックを整えるようになってから、疲れた日でも「何とかできる」と思えるようになりました。
常備食品は、料理を“がんばるためのもの”ではなく、無理しないための小さな仕組みです。
特に冷蔵・冷凍ストックは、
- 無理しない仕組みをつくるもの
- 続けやすいごはんづくりに変えてくれるもの
- 迷ったときの「助け」になってくれるもの
だと感じています。
ぜひ、あなたの暮らしに合う冷蔵・冷凍ストックを少しずつ整えてみてください。



きっと、明日の食卓がほんの少しラクに、気持ちも軽くなるはずです。
作りたくない日も助かる!常備食品の献立アイデア
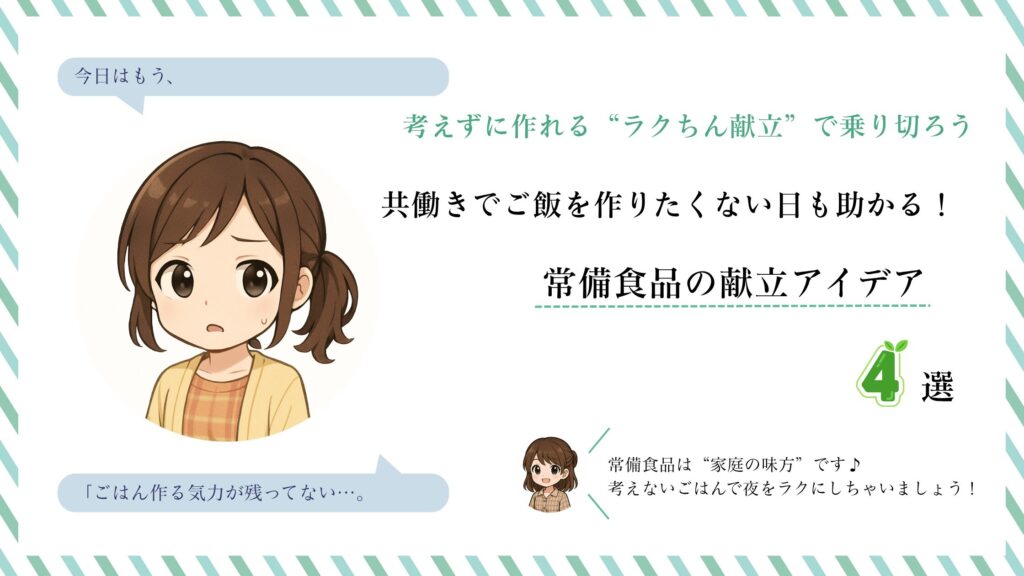
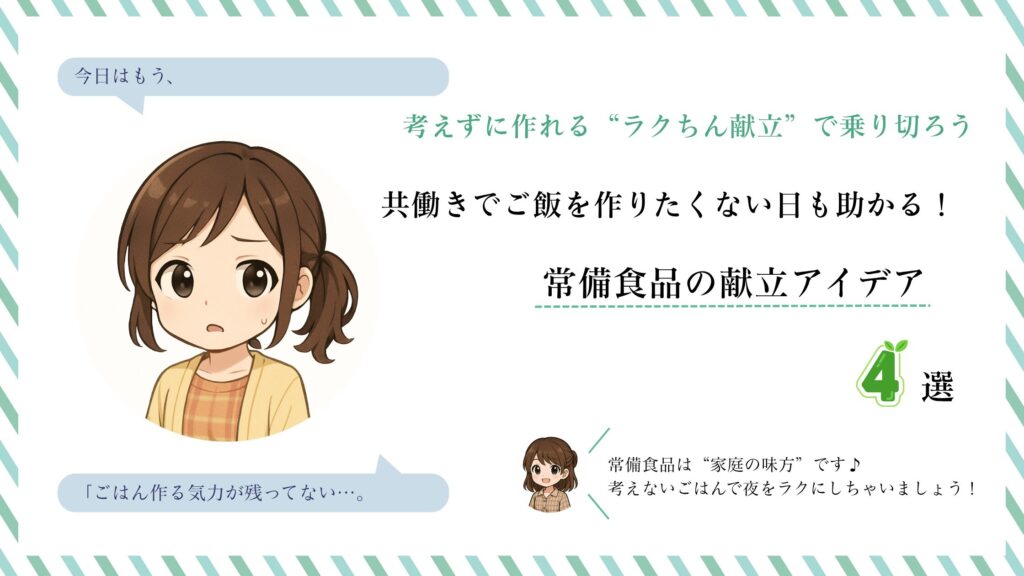
「今日はもう何も作りたくない…」
「キッチンに立つ気力もないなぁ…」
と思う日、ありませんか?



私も仕事から帰ってきて、「ご飯を作らなきゃ」と思いながらも体が動かず、キッチンに立つまでに時間がかかってしまうことが何度もあります。
でも、そんな日こそ常備食品の出番です。
常備食品をうまく組み合わせれば、
- 火を使わずに10分以内でごはんが完成
- レトルトやお惣菜に「ちょい足し」して栄養バランスを整えられる
- 無理なく、でも“そこそこ満足できる”食卓を作れる
など、少し手を抜いても、きちんとしたごはんを用意することができます。



常備食品を味方につければ、“何も作りたくない日”も無理せず回る仕組みを整えることができるんです。
この章では、作りたくない日でも無理せず整う【共働き家庭の常備食品アイデア】を、4つのパターンで紹介します。
ちょっとした工夫で“これならできそう”と思える日がきっと増えていくはずです。



そんな気持ちを後押しできるように、詳しくご紹介していきます。
1.常備食品だけで“10分以内ごはん”ができる
作りたくない日も助かる!常備食品の献立アイデアの1つ目は、常備食品だけで“10分以内ごはん”ができることです。
仕事終わりに帰宅したとき、冷蔵庫を開けて
「何も作りたくないけど、温かいものは食べたい…」
「冷蔵庫を見ても何を作ればいいかわからない…」
そんな気持ちになる日、ありませんか?



私も同じで「今日は無理かもしれない…」と思う夜は何度もありました。
でも、そんな日こそ常備食品の出番です。
常備食品をうまく組み合わせると、
- 火を使わずに10分以内で食事が完成
- 洗い物が少なく後片付けがラク
- 温かいごはんで気持ちが少し落ち着く
- 「作らなきゃ」というプレッシャーが減る
と、“今日はムリ…”という日でも心の負担を軽くできます。



私も常備食品をうまく取り入れるようになってから、「今日はもう疲れた…」という日でもご飯づくりの負担がぐっと軽くなりました。
ちなみに、我が家でよく登場する「常備食品だけごはん」はこんな感じです。
- 冷凍ご飯 + 納豆 + 刻みネギ + インスタント味噌汁
レンチン+混ぜるだけ - 冷凍パスタ + わかめスープ
温めてお湯を注ぐだけ - パックごはん + 冷凍から揚げ(レンジ加熱) + サラダチキン
メインはレンジで完結 - レトルトカレー + トマト + ゆで卵
「のせるだけ」でバランスUP
どれも包丁いらずで手早く作れるので、準備にかかる時間はほんの数分です。
「料理」というより“並べるだけのごはん”ですが、十分に食事として成り立ちます。



こんな日があってもいいですよね。
大切なのは、無理なく続けられる形にしていくことです。
常備食品に頼ることは「手抜き」ではなく、無理をしないための工夫です。
毎日完璧を目指す必要はありませんし、頑張れない日があってもいいと思います。
まずは、「これならできそう」と思える簡単パターンを1つだけ作ってみてください。



それだけでも、明日の夕飯が少しだけラクに感じられるはずです。
2.「ご飯+レトルト+野菜」で時短どんぶりごはん
作りたくない日も助かる!常備食品の献立アイデアの2つ目は、「ご飯+レトルト+野菜」で時短どんぶりごはんを作ることです。
仕事や家事で疲れている日ほど、
「できるだけ火を使いたくない…」
「洗い物も増やしたくない…」
そんな気持ちになりますよね。



私も同じで、帰宅後に料理へ気持ちを切り替えるのが難しい日がよくあります。
そんなときに助かるのが、レトルト食品を使った“のせるだけどんぶり”です。
ご飯とレトルトを温めて、常備している野菜や卵を添えるだけ。ほんの数分で食事が整います。
時短どんぶりのうれしいポイントとして、
- 洗い物が少ないので、後片付けがすぐ終わる
- レトルトの種類が豊富なので飽きにくい
- 野菜や卵を足すだけで栄養バランスが整う
- どんぶり1つで満足感のある食事になる
ほんのひと手間で「ご飯を整える」ことができるのが、時短どんぶりの魅力です。



レトルトは「手抜き」ではなく、無理せず食事を用意するための立派な選択肢だと思います。
では、我が家でよく登場する時短どんぶりを紹介していきましょう。
- パックごはん + レトルトカレー + トマト
温めて“のせるだけ” - 冷凍ご飯+中華丼の素+冷凍カット野菜
具材はレンジ加熱ですぐ完成 - パックごはん + 親子丼の素 + サラダチキン
たんぱく質も確保しやすい - ご飯+レトルト牛丼の素+温泉卵+刻みねぎ
定番でも満足感◎
どんぶりごはんは、疲れた日ほど助けになる味方です。
火を使わなくても作れますし、野菜やたまごを少しプラスするだけでバランスも整えられます。



ご飯づくりは、完璧を目指す必要はありません。
まずは、「これならできそう」という組み合わせを1つだけ決めておくことから始めてみてください。
選択肢があるだけで迷いが減り、「今日はこれでいこう」と気持ちがラクになります。



疲れた日は、ぜひ“ご飯+レトルト+野菜”の時短どんぶりを味方にしてくださいね。
3.ご飯を作らない日は“買う+足す”でOK!整う食卓の作り方
作りたくない日も助かる!常備食品の献立アイデアの3つ目は、“おかずを作らない日”はスープや惣菜をうまく組み合わせることです。
仕事や家事で疲れ切った日、
「今日はもう何も作れない…」
「キッチンに立つ気力が残っていない…」
そんな日もありますよね。



私も同じで、どれだけ工夫していても「今日は正直ムリ…」という日は必ずあります。
でも、そんな日は無理に作らなくて大丈夫です。
ご飯づくりを無理なく続けようと意識していても、疲れがたまると限界はきてしまうものです。
そんな日は、無理に作ろうとせず、“整えるだけ”のごはんに切り替えるのがおすすめです。
ポイントはとてもシンプルで、
- お惣菜やお弁当を「メインのおかず」にする
- 常備食品で「不足しがちな栄養」をちょい足しする
この2つを意識するだけで、罪悪感のない・整ったごはんになります。



我が家の場合ですが、“ご飯を作らない日”は次のように組み合わせています。
- スーパーのお弁当を購入+自宅にあるインスタント味噌汁
- 惣菜コロッケ+サラダを購入+インスタント味噌汁を追加
- チルド惣菜(ハンバーグ)を購入+ごはん+具だくさんスープ(フリーズドライ)を追加
- コンビニサラダを購入+冷凍焼おにぎり+カップスープ
お惣菜やお弁当を買うだけで済ませるのではなく、常備食品を少し足すことで“必要な栄養を補えるごはん”になります。



スープやサラダをほんの少し添えるだけで、きちんとした食事ができるのも、嬉しいポイントではないでしょうか?
料理は“毎日当たり前にやるもの”と思われがちですが、休む日があるから続けられるのだと思います。
まずは、あなたなりの“作らない日の形”をひとつ決めておくことから始めてみてください。



常備食品を少し足すだけでも、「今日は無理かも…」という日を安心して乗り切ることができるようになりますよ。
4.常備食品は家電と組み合わせるともっとラクになる
作りたくない日も助かる!常備食品の献立アイデアの4つ目は、調理家電を組み合わせた“火を使わない調理”です。
仕事終わりに帰宅したとき、
「火を使うのも面倒…」
「今日は台所に立ちたくない…」
そんな日ってありますよね。



私も同じで、正直「今日はもう体力ゼロ…」という日はたくさんあります。
仕事をして帰ってきて、そこからご飯づくりや片付け、洗濯まで…と思うと、気力が追いつかない日もあるものです。
そんなときに助けられているのが、ホットクックや電子レンジなどの調理家電です。
火を使わずに調理できる家電は“ほったらかしでOK”のものも多く、手を動かす時間を減らしながら温かい食事を用意できるのが魅力です。



常備食品と同じように、調理家電を活用することで得られるメリットがあります。
- 火加減を見る必要がなく、調理の負担が減る
- “放置調理”ができるので、その間に他の家事や休憩ができる
- 温めや下ごしらえが手早くでき、時短につながる
- 常備食品との相性が良く、一品追加がしやすい



わが家でも、疲れた日ほど「常備食品×調理家電」の力を借りています。
例えば、次のような組み合わせが多いです。
- 電子レンジ × 冷凍ハンバーグ
温めてトマトやレタスを添えるだけで、一皿ごはんに - ホットクック × 常備野菜+冷凍肉
材料を入れてボタンを押すだけで、煮込み料理が完成 - レンジ調理プレート × 冷凍魚
フライパンいらずで焼き魚ができる
調理家電があるだけで、料理にかける体力や気力をぐっと抑えられます。
「今日は台所に立つのがしんどい…」という日でも、常備食品と組み合わせることで、無理のない形で食事を整えられるのが良いところです。
どうしても、調理家電というと「難しそう」「ハードルが高そう」と感じる方もいるかもしれません。
ですが、電子レンジだって立派な調理家電です。



まずはレンジ調理から気軽に取り入れてみるのも十分です。
常備食品と調理家電を組み合わせることで、がんばらなくても食事を整えられる日が増えていきます。
そんな日を助ける“仕組み”を持っておくことが、共働きのごはんづくりを無理なく続けるコツです。



無理をしない仕組みがあれば、毎日のごはんはもっと気楽になります。
ぜひ、試してみてくださいね。
作れない日があるからこそ、助けになる仕組みを持っておくことが大切だと感じています。
\関連記事はこちら/
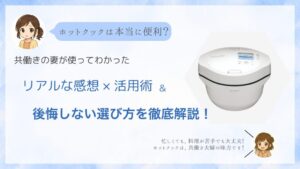
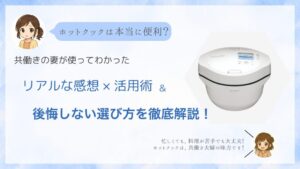
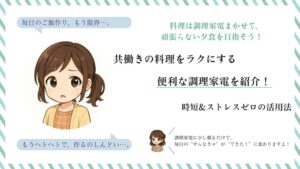
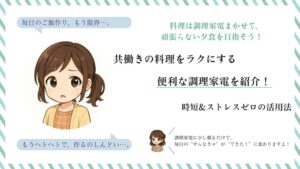
この章では、「作りたくない日」を無理なく乗り越えるための常備食品アイデアをご紹介しました。
- 常備食品だけで“10分以内ごはん”ができる
- 「ご飯+レトルト+野菜」で時短どんぶりごはん
- ご飯を作らない日は“買う+足す”でOK!整う食卓の作り方
- 常備食品は家電と組み合わせるともっとラクになる
共働きで忙しい日が続くと、料理はどうしても負担に感じてしまうものです。
でも、常備食品をうまく使えば「がんばらなくても整うごはん」は十分に作れます。
大切なのは、「作れない日があっても大丈夫」という考えを持つことです。
ごはん作りは毎日のことだからこそ、頑張らない選択肢を持つことが続けるコツになります。



私も、常備食品と今回紹介した4つの方法を組み合わせるようになってから、「今日はこれでいい」と素直に思える日が増え、心が本当にラクになりました。
常備食品は、手抜きではなく“暮らしを支える味方”です。
疲れた日や余裕がない日は、少し力を抜いてもいいのではないでしょうか。
ぜひ、あなたも“無理をしないごはん作りのパターン”をひとつずつ増やしてみてください。



きっと、毎日の食卓が今よりもっと気楽で続けやすいものになっていくはずです。
常備食品をムダなく使い切るストック管理のコツ
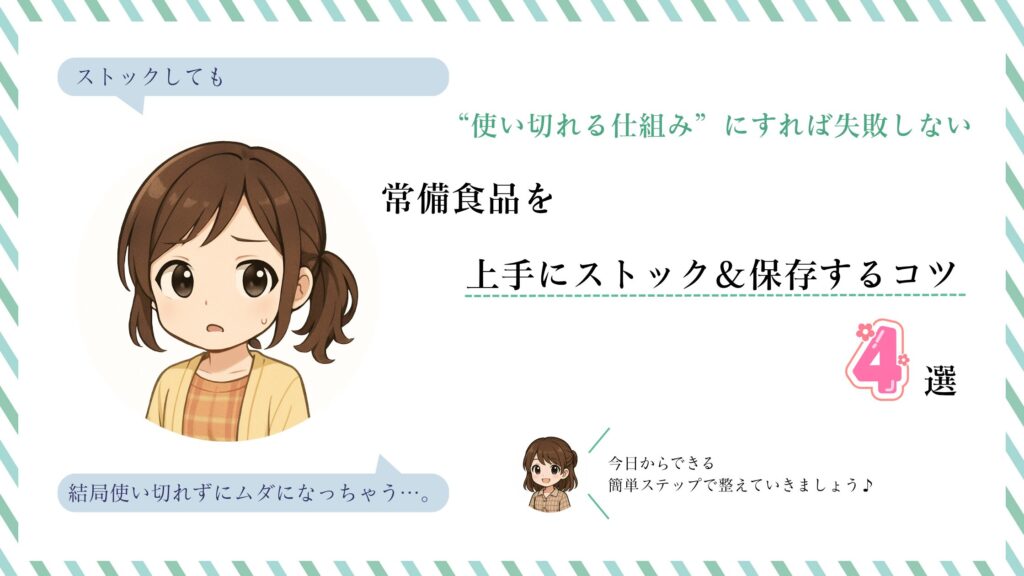
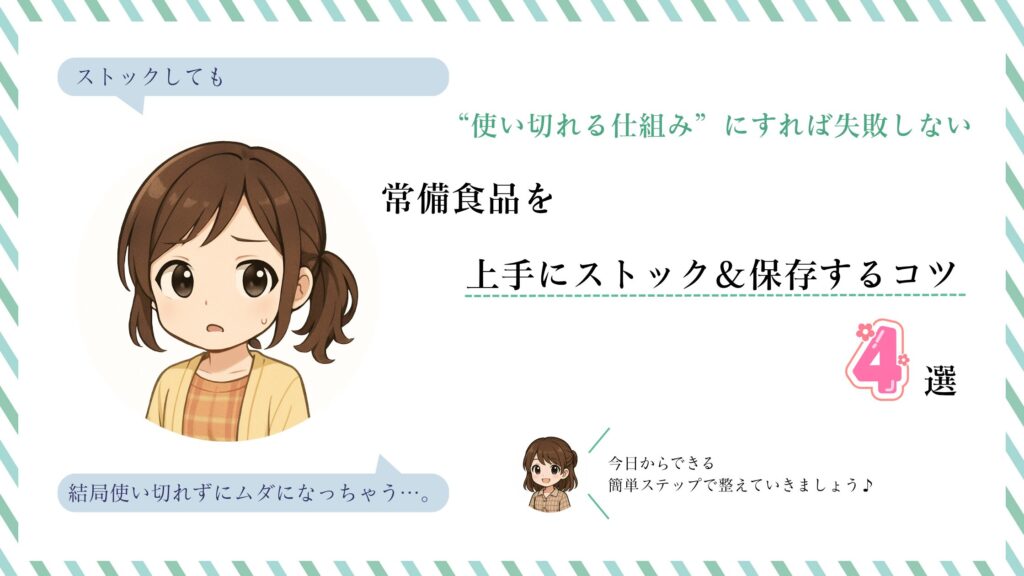
常備食品のストックは、共働き家庭にとってごはん作りの負担を減らしてくれる心強い味方です。
しかし、「ストックを持つこと」よりも難しいのは、実は管理しながら使い切ることではないでしょうか。
冷蔵庫や食品棚を開けてみたら…
- 同じ食材を二重買いしていた
- 奥から賞味期限切れのレトルトが出てきて落ち込んだ
- 「あると思っていた食材がない」「どこに置いたっけ?」と探し物ばかり
そんな経験はありませんか?



私も以前はまさにこの状態で、週末に気合いを入れて買い出ししても、管理が追いつかずにムダにしてしまうことがよくありました。
せっかく節約や時短のために始めたストックなのに、気づけばそれが“心の負担”になっていたんです。
でも、ストック管理がうまくいかないのは性格ややる気の問題ではありません。
使い切るための仕組みが整っていないだけなんです。
この章では、私たち共働き夫婦でも無理なく回せるようになった、ストックと保存をラクに続けるための4つのコツをご紹介します。
どれも特別な道具や難しいテクニックは必要ありません。
ちょっとした仕組みを取り入れるだけで、ストックは「面倒な在庫管理」から「心と時間のゆとり」に変わります。



それでは、ひとつずつ見ていきましょう。
1.ストックを管理しやすくする収納のコツ
常備食品を上手にストック&保存するコツの1つ目は、ストック収納を工夫することです。
「買い置きしたのに、どこに置いたか分からない…」
「同じ調味料をまた買ってしまって、在庫が増えていく…」
そんな経験はありませんか?



私も“空いているところにとりあえず置く”という収納だったので、棚の中はごちゃつきやすく、在庫をきちんと把握できていませんでした。
その結果、
- 賞味期限が近いものに気づかず慌てて使う
- あるのに気づかず、また買ってしまう
- どこに何があるか探すだけで疲れる
ということがよくありました。
でも、これは「性格の問題」でも「片付けが苦手だから」でもありません。
原因は仕組みがないままストックしていることでした。
そこで意識したのが、“見える・取り出しやすい・戻しやすい”収納に変えることです。



共働き家庭のように平日は時間との勝負になる暮らしでは、共働きの常備食品こそ「管理のしやすさ」が大切だと気づきました。
私が取り入れてよかった方法はこの4つです。
- カテゴリ別に分ける(箱を使うだけ)
主食/レトルト/スープ/乾物など、種類ごとにボックスに分けてラベリング - 先に買ったものから使う仕組みを作る
新しいものは奥、古いものは手前へ。賞味期限はマステでひと目管理 - “一軍ゾーン”をつくる
よく使うものだけを手前や目線の高さに置いて、探す時間をゼロに - 週1回、3分だけ在庫リセット
減ったものをメモして補充。無駄買いや買い忘れが自然に防げる



この方法に変えてから、「あるのに見つからない」ストレスがなくなり、買い物の効率や節約にもつながりました。
共働き夫婦にとっては、
- 常備食品は“量より仕組み”を整えること
- 時短につながる収納方法を見つけておく
この2つが重要なポイントになってきます。
とはいえ、無理して完璧を目指さなくて大丈夫です。
週末にボックスを3つ用意して分けるだけでも、翌週のごはんづくりが本当にスムーズになります。



少し「めんどくさい」と感じてしまうかもしれませんが、ぜひ、やってみてください。
ストック収納の工夫をする前とした後では、使い勝手が変わっているはずです。
2.まとめ買いした食材を小分け冷凍してムダを防ぐ
常備食品を上手にストック&保存するコツの2つ目は、まとめ買いした食材を小分け冷凍することです。
共働き家庭では週末にまとめ買いをすることが多いと思いますが、買ってきた肉や魚をそのまま冷凍庫へ入れてしまい、
「冷凍焼けしてパサパサになっていた…」
「一部だけ使いたいのに、全部解凍することになった…」
という経験はありませんか?



私も同じでした。
「ちょっとだけ使いたいのに不便…」「結局メニューを変えて対応…」という小さなストレスが積み重なっていました。
そこで役に立ったのが、小分け冷凍です。
小分け冷凍には
- 必要な分だけサッと使える
- 解凍が早くなり、時短につながる
- 冷凍焼けしにくく、食材の鮮度を保ちやすい
- 調理の選択肢が増え、平日の迷いが減る
特に忙しい共働き家庭にとって、小分け冷凍は料理の準備を早くする仕組みづくりになります。



私も使いやすい分量に分けて保存するだけで、使い忘れや解凍の手間がぐっと減り、悩みを解消できました。
でも、小分けって、
- 手間がかかりそう
- 鮮度が心配
- 冷凍庫がパンパンになる
- 管理が難しそう
など、「結構手間じゃないの?」と思うかもしれません。
実は特別な道具もテクニックも不要で、次の3ステップだけでできます。
- 使いやすい分量に分ける
鶏むね肉1枚ずつ/豚こま150gずつ/ひき肉100gなど - 平らに薄く伸ばして包む
一般的なラップやフリーザーバッグでOK
空気を抜くと鮮度キープできる - 冷凍庫で立てて保存
カテゴリごとに袋を分けると在庫管理もしやすい



※真空保存タイプの袋や密着ラップ(グラッド プレスンシール)は、より鮮度を保ちたい人におすすめです。
最初から完璧を目指す必要はありません。
まずは、1種類だけ小分け冷凍にしてみてください。



私は週末の買い物後、ひき肉だけ・鶏むね肉だけなど無理のない範囲で続けています。
小さく始めれば負担なく続けられますし、「平日がラクになる」という実感がわくはずです。
小分け冷凍は、忙しい毎日の“小さな助け”になります。
まずは、無理なく小分け冷凍できる量から、気軽に取り入れていきましょう。



そうすることで、忙しい日でも「なんとかなる」って思えるようになりますよ。
3.賞味期限を管理しやすくするちょっとした工夫
常備食品を上手にストック&保存するコツの3つ目は、賞味期限を管理しやすくする仕組みを作ることです。
共働きの生活では忙しさからキッチンの管理が後回しになりがちで、気づいたら
「買ったことを忘れて同じ食材をまた買ってしまった…」
「ストック棚の奥から、賞味期限3か月前のカレーが出てきた…」
など、こういう経験をしたことってありませんか?



私も以前は同じでした。
ストックをうまく使い切れず、気づけばムダ買いや食材ロスが増える悪循環に悩んでいました。
賞味期限管理がうまくいかない一番の原因は、性格や管理能力の問題ではありません。
実は、
- 仕組みがないから迷う
- 迷うから放置
- 放置してムダになる
という流れが起きているだけなんです。
だからこそ必要なのは、「頑張って管理すること」ではなく、迷わず続けられる“ちょっとした仕組み”を作ることです。



我が家でも以前はストック棚の奥から賞味期限切れの食品が出てきて、「これ、いつの?」と夫に聞かれたことがあります…。
そこで試してみたのが、ムリなく続けられる小さなルールづくりです。
特別な道具もいらない、シンプルな3つの方法はこちらです。
- 賞味期限を“見える化”する
-
- 買ったらすぐマスキングテープに期限を書いて貼る
- 表記は「3/28まで」など一目で読めるように
- ストック棚・冷凍庫でも探しやすくなる
- 使う順番を決める(先入れ先出しルール)
-
- 新しい物は奥、古い物は手前に置く
- ジャンル別に収納すると迷わない(例:主食/レトルト/スープ)
- 週1回“在庫リセットタイム”を作る
-
- 減った食材に印をつける
- 期限が近いものを前に集める
- 「使い切りたい食品メモ」を冷蔵庫に貼る
この3つを意識するだけで、ムダ買いが減ってストック管理がぐっとラクになります。



毎日の食事作りがラクになるだけでなく、買いすぎ防止にもつながるのが嬉しいポイントです。
忙しい毎日の中で、完璧に管理しようとすると疲れてしまいます。
だからこそ、がんばるのではなく迷わない仕組みを作ることが大切です。
ちょっとした工夫でも「ちゃんと回っている」という感覚が生まれるだけで気持ちはラクになるものです。



できることから整えていけば、ストック管理は無理なく続けられるはずです。
4.定期的なローテーションで使い忘れを防ぐ
常備食品を上手にストック&保存するコツの4つ目は、定期的なローテーションを取り入れて使い忘れを防ぐことです。
共働きの暮らしでは、平日は仕事でバタバタして買い物や調理が精一杯になり、気づけば、
「冷凍庫の奥から、いつ買ったかわからない肉が出てきた…」
「ストック棚を片付けたら、同じレトルトカレーが5個もあった…」
など、食品の管理まで手が回らないことも多いですよね。



正直、「ストックして安心」までは良いのですが、そのまま使い忘れてしまうことが何度もありました。
当時は「私って片付けや管理が苦手なのかな…」と思っていましたが、原因は“使い切る仕組みがなかった”だけだったんです。
そこで私が始めたのが、定期的に在庫を見直して使う順番を整える“ローテーション”という方法です。
大げさな管理ではなく、在庫を見直して使う順番を整えるだけで、ストックが自然に回る仕組みを作ることができます。



実際にやってみて「これなら続けられる」と感じた、シンプルな方法を3つ紹介します。
- 収納位置を固定する
-
- 賞味期限が近いものは手前、新しいものは奥にする
冷蔵・冷凍・常温ストックごとに定位置を決めるだけで、在庫がひと目で把握できるようになる
- 賞味期限が近いものは手前、新しいものは奥にする
- “使い切りボックス”を作る
-
- 期限が近いものや半端に余った食材は、使い切りボックスに入れる
「今週中に使うもの」とラベリングしておくと、迷わずここから使えるようになる
- 期限が近いものや半端に余った食材は、使い切りボックスに入れる
- 週1回の“在庫リセットタイム”
-
- 週末の3分だけ在庫をチェックして整える習慣をつける
減ってきた食材を書き出すだけでもムダ買いを防げるようになる
- 週末の3分だけ在庫をチェックして整える習慣をつける
大事なのは「きっちり管理すること」ではなく、迷わず使える状態を作ることです。
まずは、
- 冷蔵庫の調味料コーナーだけ見直す
- レトルト食材だけ“使い切りボックス”を使う
- 日曜の夜だけ3分在庫チェックする
このように小さく始めるだけでも、ストックの使い忘れは確実に減ります。
ローテーションは、忙しい共働き家庭でも無理なく続けられる方法です。
ストックを“貯めるだけ”から“使い切れる”流れに変えることで、ムダが減って管理のストレスも軽くなります。



少しずつ整えていけば大丈夫です。
小さな前進の積み重ねが、暮らしをちゃんとラクにしてくれますよ。
この章では、共働き家庭でもムリなく続けられる常備食品を上手にストック&保存するコツについて詳しくお話ししてきました。
- ストック収納の工夫
- まとめ買いした食材を小分け冷凍してムダを防ぐ
- 賞味期限を管理しやすくするちょっとした工夫
- 定期的なローテーションで使い忘れを防ぐ
共働きの暮らしでは、料理にかけられる時間や体力には限りがあります。
だからこそ、常備食品は「たくさん持つこと」よりも、必要なときにすぐ使える状態を保つことが大切です。
そのために必要なのは、がんばって管理することではありません。
自然に使い切れる仕組みをつくることが、ストック管理をラクにする近道です。



私も以前は常備食品を持て余し、使い忘れやムダ買いに悩んでいたんです。
しかし、この4つのコツを取り入れたことで、食材管理のストレスがぐっと減り、ムダ買いも防げるようになりました。
共働きの暮らしは忙しいからこそ、完璧を目指す必要はありません。
小さく整えることを積み重ねれば、常備食品は負担ではなく毎日を支える味方になります。



少しずつ前に進めば大丈夫です。
あなたの暮らしに合う形で整えていきましょうね。
まとめ|常備食品があれば「作りたくない日」も安心
この記事では、共働き 常備食品を中心に、忙しい平日の“あと一品”や時短どんぶりの作り方、ストック&保存のコツについても詳しくお伝えしてきました。
- 共働き夫婦にとって「常備食品」が心強い理由
- 我が家で役立った常備食品リスト【常温ストック編】
- 冷蔵庫・冷凍庫に常備しておきたい食材
- 作りたくない日も助かる!常備食品の献立アイデア
- 常備食品を上手にストック&保存するコツ
毎日のごはん作りは、「気力との勝負」になる日がありますよね。
仕事で疲れた日や余裕がない日は、「今日はもう作れないかも…」と思うことがあって当然です。
そんなときに支えになってくれるのが、常備食品という“仕組み”です。



常備食品は、料理を頑張るためのものではなく、がんばらなくても食事を回せる安心を増やすものだと感じています。
完璧じゃなくても、あなた自身が続けられる形で大丈夫です。
まずは次の“小さな一歩”から始めてみませんか?
- パックごはんを2つ置く
- レトルト食品を2種類決める
- インスタントスープを2つストックする



まずは「主食2・レトルト2・スープ2」だけで十分です。
無理をしない備えがあると、「今日は作れない日」も安心して過ごせるようになります。
とはいえ、常備食品だけでは解決しきれない悩みもありますよね。
ごはん作りの悩みは、「原因」「解決策」「仕組み」の3つを整えることで少しずつラクになっていきます。
ここからは、ごはん作りの負担そのものを軽くしていけるよう、一歩ずつ一緒に整えていきましょう。



「もう少し深く知りたい」「次のステップに進みたい」という方へ、目的別に記事をまとめました。
\ご飯づくりがつらくなる原因を整理したい方はこちら/
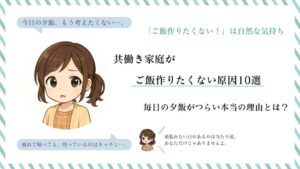
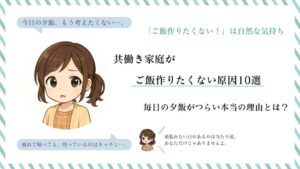
\無理のない解決策も知りたい方はこちら/
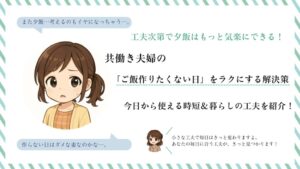
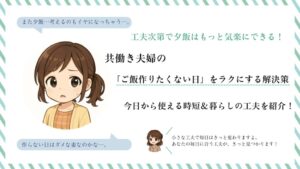
\もっと時短を進めたい方はこちら/
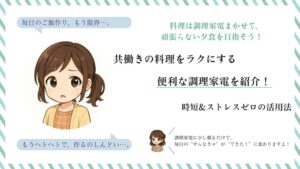
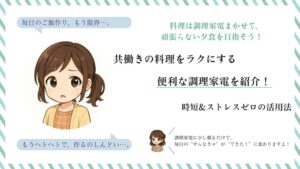
\罪悪感を手放して気持ちを軽くしたい方はこちら/


\シリーズ全体をまとめて見たい方はこちら/
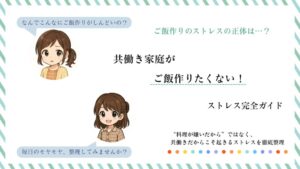
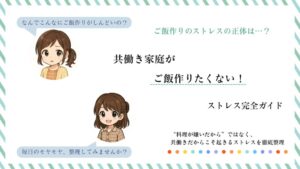
無理をせずに整える食卓は、少しの準備から生まれます。
焦らなくて大丈夫です。



あなたの暮らしに合うリズムを、少しずつ見つけていきましょう。

